【重要なお知らせ】 このたびクリニックフラウ栄は、2025年9月より「レディースクリニックフラウ名駅」として新たにスタートいたします。 ◆ 現在のクリニックでの診療:2025年8月13日(水)まで ◆ レディースクリニックフラウ名駅:2025年9月1日(月)より診療開始予定 ※名古屋駅より徒歩2分 ※ご予約方法・電話番号に変更はございません ※詳細につきましては、ホームページやLINEにて順次ご案内いたします これからも、女性の心とからだに寄り添うクリニックとして努めてまいります。 今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。


3. 婦人科で取り扱う主な疾患と治療法
4. 当院の婦人科検査について
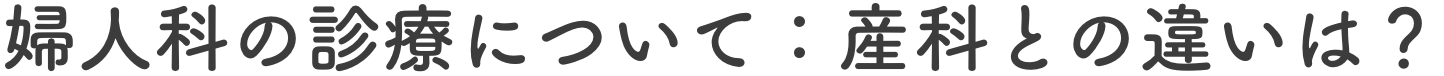
婦人科と産科の大きな違いは、出産に関連した診察をするかしないかです。婦人科は出産と関連しない女性の症状に対して、検査や診察を行います。一方で産科は出産に関連する検査や診察を行います。
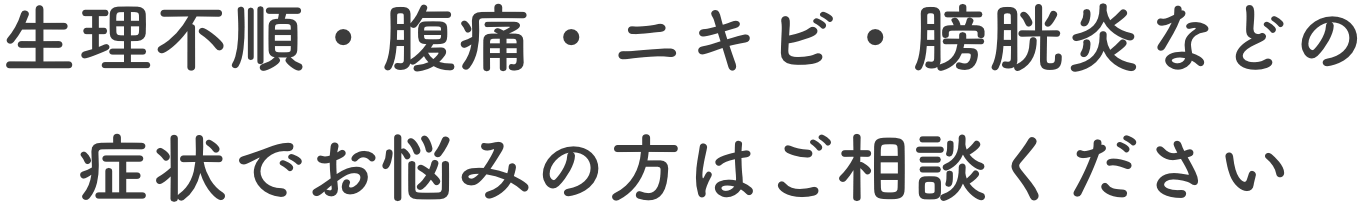
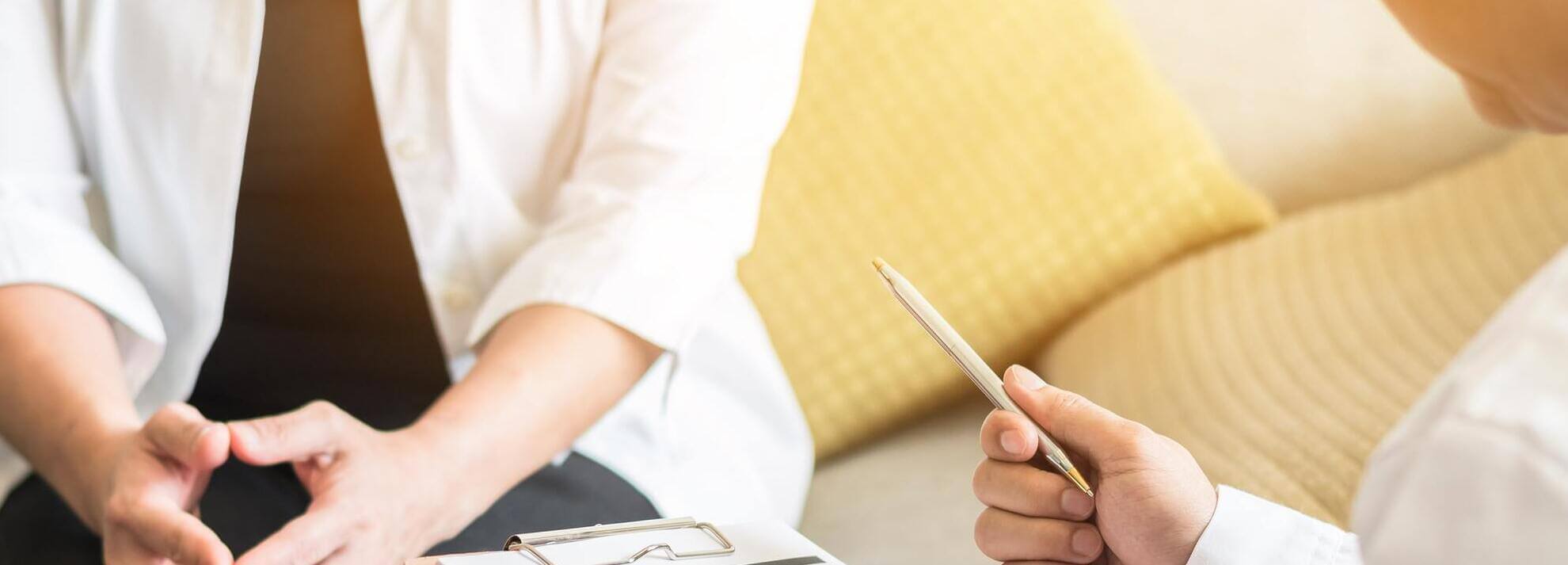
当院では、女性のライフスタイルを総合的にサポートします。以下のような女性の病気や疾患についてご相談ください。
Webで予約する
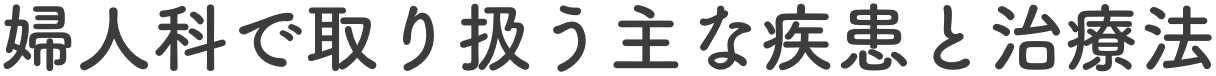

当院での主な疾患と治療方法について説明します。
卵巣から分泌される女性ホルモンの不足や分泌のバランス異常によって、卵巣が正常に働いていない状態のことです。主な症状は生理不順や不正出血です。体質的なもので原因が分からないことも多いですが、高プロラクチンや甲状腺異常、多嚢胞卵巣症候群がその原因となっていることがあります。
現在、妊娠を希望していなくて、生理不順や不正出血でお困りの場合は、低用量ピルを服用することで症状は改善されます。
子宮筋腫は子宮の筋肉の部分に良性のコブができる病気です。主な症状は月経が増えることと月経痛です。その他に月経以外の出血、腰痛、頻尿などの症状があります。筋腫ができる原因ははっきりとは分かっていませんが、卵巣から分泌される女性ホルモンによって大きくなることは分かっています。そのため、閉経後は大きくなりません。
筋腫があっても日常生活に差し支えがなければ経過観察をします。ホルモン剤による治療で子宮筋腫を小さくします。状態によっては手術が望ましい場合もあります。
子宮内膜は子宮の内側にしかないはずですが、子宮内膜によく似た組織が内膜以外の場所に発生し、卵巣や子宮などがおおきく腫れる病気です。
子宮内膜症の原因は、はっきりとは分かっていませんが月経のある女性の数%~10%程度がこの病気をもっているだろうと推定されています。主な症状は生理痛ですが、生理中以外の時にも性交渉あるいは排便時の痛み、腹痛や腰痛が起こり、不妊症の原因にもなります。
治療方法は症状や重症度、ライフスタイルを総合的に判断し、薬(ホルモン剤や痛み止め)での治療か手術をするのかを考えます。
卵巣腫瘍とは卵巣にできる腫瘍のことです。良性腫瘍、境界悪性腫瘍、悪性腫瘍に分かれます。良性の卵巣腫瘍の中で一番多いものは卵巣嚢腫です。
卵巣嚢腫は卵巣内に液体や脂肪などが溜まる病気ですが、中には子宮内膜症が卵巣内に発生し月経の度に出血した血液が溜まることで起こるものもあります。
子宮内膜症が原因のものは、よく「卵巣チョコレート嚢腫」と呼ばれます。初期にはほとんど症状はありませんが、大きくなってくると腹痛や腰痛、頻尿や便秘などの症状が現れます。チョコレート嚢腫の場合は子宮内膜症の治療薬を投与します。その他の卵巣嚢腫については経過観察をします。がんが疑われる場合には手術が勧められます。
PMSとは月経前に3~10日間ほど続く心と体に現れる不調のことです。主な症状としては、ストレスを感じる、浮腫、イライラ、乳房痛、無気力などがあります。月経がはじまると症状は軽くなったり、なくなったりすることが特徴です。
はっきりとした原因は分かっていませんが、女性ホルモンのバランスが急激に変化することにより、脳内のホルモンや神経伝達物質の異常を引き起こすことが関係しているのではないかと言われています。
低用量ピルを服用することによって、排卵を抑制すると女性ホルモンのバランスが急激に変化することがなくなるため症状は改善されます。
参考:日本産婦人科学会|月経前症候群(PMS)
性感染症とは、性交渉によって感染する病気の総称です。カンジダは性交渉によってうつるのではなく、膣内の常在菌のバランスが崩れることによって発症するため、厳密には性感染症ではありませんが、オリモノが気になって相談される一番多い疾患です。
性感染症は初期には自覚症状がない場合が多く、また症状のない時にもパートナーに感染させてしまいます。また、自然に治癒することもなく、放置をすることで不妊症になることもあります。心当たりのある時は診察をして、早期に検査と治療をすることが大切です。
更年期とは、日本では閉経の前後5年の10年間を指します。この時期に現れる様々な症状があり、日常生活に支障をきたす場合を更年期障害といいます。
主な症状は、以下の6つです。
現時点では更年期障害の明確な診断基準はなく、診察によって総合的に判断し治療を開始します。女性ホルモンの濃度は、閉経後2年を経過するぐらいまでは大きく変動するため更年期障害の診断に血液検査をして女性ホルモン濃度を調べることは有用ではありません。治療法は漢方治療やホルモン治療などですが、必要に応じて精神科治療も並行して開始します。
Webで予約する
妊娠を望む男女が避妊をしないで性交をしているにもかかわらず、1年間妊娠しないものをいいます。原因は女性ホルモンが関係している場合や子宮や性感染症、免疫などが関係するものもあります。当院ではブライダルチェックでホルモンの検査や不妊の原因となる性感染症がないかを調べます。
Webで予約する


当院で診察の際に行う検査を紹介します。
婦人科的な診察(内診)の際に使用する超音波検査装置です。膣を通して(膣の中に入れて)骨盤内の状態を観察しますが、主に子宮、卵巣を詳しく見ることができ、子宮筋腫や子宮内膜症、卵巣嚢腫、卵巣腫瘍などがわかります。お腹から超音波検査するよりもより精細な状態観察をすることができます。
婦人科疾患を調べる検査として最も簡便で不可欠な検査方法です。
ただし性交渉が未経験の方の場合は、超音波検査の検査プローブの先端が膣の中を通りますので、痛みを伴うことが多く、あまりおすすめはしませんので、お腹から超音波検査することもあります。
当院では妊婦健診は行っておりませんが、現在の妊娠の有無についてはお調べ可能です。必要に応じて産科施設への受診をすすめたり、当院で対処を検討したりします。
尿検査には主に以下の2種類があります。
Webで予約する


当院では目的に応じて、低用量ピル、月経移動(中用量)ピル、緊急避妊ピルを処方します。


子宮頸がんは20代~30歳代の女性がかかるがんの中で、最も多いがんです。当院では、問診と子宮頸部細胞診の検査で確認します。
子宮がん検診の精密検査では以下の検査を行います。

妊娠や出産に影響がある病気の有無をチェックする目的で行います。子宮や卵巣の病気、性感染症は初期には自覚症状のないことが多く、病気を放置すると、不妊症や赤ちゃんの先天的な病気につながることもあります。妊娠を意識したら受けて欲しい検査です。当院は女性専用クリニックのため男性のブライダルチェックは行っておりません。
ブライダルチェックは保険適用外(自費)の検査になりますが、検査に該当する症状のある項目は、保険適用の対象になります。


性感染症とは、性交渉によって感染する病気の総称です。性器の接触だけでなく、オーラルセックスやアナルセックスによって、性器以外にも感染します。主に以下の8種類に対する検査を行っております。
以下ページでは各病気の原因や症状、検査方法を詳しく説明しておりますので、気になる方はぜひご覧ください。

症状のある方、精密検査をご希望の方、治療を要する方はすべて保険診療の対象となります。保険証を必ずお持ち下さい。保険診療ですと費用は2,000円~5,000円程度になります。
自由診療の場合はこちらの料金表、各メニューの料金が記載してありますのでご覧ください。


婦人科を受診する際のよくある疑問や悩みについてお答えします。
生理中に受診していただいても大丈夫です。子宮がん検診の精密検査で「生検」の検査が必要な場合は、生理中は避けていただく必要がありますが、検診は可能です。
婦人科の受診は緊張や不安になることが多いと思います。当院では少しでもリラックスできるように、ゆったりとした待合室にしております。また、不安が強い場合にはスタッフがサポートしますのでお声掛けください。
痛みの感じ方には個人差がありますが、体の力が入るほど痛みは強く感じます。ゆっくりと呼吸をすることで、体の力が抜けて痛みは少なくなります。ご心配な場合はスタッフへお声掛けください。
※性交渉の経験がない方は原則的には内診の検査は行いません。
内診の検査を行うことがありますので、着脱しやすい服装をおすすめします。可能であればストッキングやタイツではなく靴下の方がスムーズに診察が終わります。 生理日の移動や緊急避妊ピルの処方を希望する場合には、内診の検査は行いませんので服装は問いません。
Webで予約する